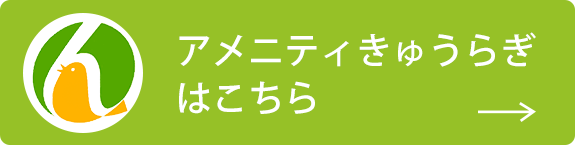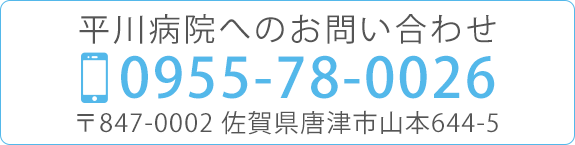厚生労働大臣が定める掲示事項
■入院基本料について
1,障害者施設等入院基本料(10対1入院基本料)
1日に入院患者10人に対して1人以上の看護職員を配置しております。なお、時間帯により看護職員の配置が異なります。
実際の看護配置につきましては、院内に詳細を掲示しておりますのでご参照下さい。
2,地域包括ケア入院医療管理料2
201号室(1名)・213号室(3名)・216号室(4名)
■入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さまに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。
■入院時食事療養について
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しています。なお、夕食については個々の患者さまの病状に応じ午後6時以前に提供する場合もあります。
■当院では、九州厚生局に以下の届出を行っています。
(1)基本診療料の施設基準等に係る届出
■医療DX推進体制整備加算 ■障害者施設等入院基本料(10対1) ■診療録管理体制加算3
■特殊疾患入院施設管理加算 ■感染対策向上加算3 ■データ提出加算 ■地域包括ケア入院医療管理料1
(2)特掲診療科の施設基準等に係る届出
■がん性疼痛緩和指導管理料 ■がん患者指導管理料 ■電子的診療情報評価料
■別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院
■在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
■在宅がん医療総合診療料 ■CT撮影及びMRI撮影(16列以上64列未満のマルチスライス)
■脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) ■運動器リハビリテーション料(Ⅱ)
■がん患者リハビリテーション料 ■医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
■胃瘻造設時嚥下機能評価加算 ■外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ■入院ベースアップ評価料(15)
(3)その他の届出
■酸素の購入価格の届出 ■入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)
■明細書発行体制加算について
医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬算定項目の判る明細書を無料で発行しています。明細書は、使用した医薬品の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。その点をご理解いただき、ご家族様等が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。
■保険外負担に関する事項
当院では個室使用料、病衣使用料、テレビ使用料、証明書・診断書料などにつきまして、その利用日数、使用料、利用回数に応じた実費の負担をお願いしております。詳しくは以下の料金表をご参照ください。
【実費徴収に係るサービス内容及び料金について】 ※料金はすべて消費税込みの料金です。
◇病衣貸与料 1日につき 90円
1日につき 200円 ※つなぎ服貸与時
◇テレビ利用料 10,500/月(1日当たり 350円)
※月締めで1ヶ月に満たない場合は日割り計算致します。 (特別室のテレビ利用料は無料)
◇クリーニング料
1か月 4,000円(1日当たり 130円)
※業者との契約になります。ご希望の方は看護師または受付にご相談下さい。
※月締めで1ヶ月に満たない場合は日割り計算致します。
◇健康診断料 <定期> 7,400円 <その他> 検査項目により変更有
◇検査食 クリアスルー 1,100円
◇診断書料・証明書
(診断書名) (料金/1通)
①各種証明書(簡単なもの) 1,100円
②交通事故診断書(警察提出用) 2,200円
③自賠責請求用診断書 4,400円
④自賠責請求用診療報酬明細書
3,300円
⑤生命保険用診断書 5,500円
⑥死亡診断書
11,000円
※2通目から 2,200円
⑦年金診断書(肢体の障害用)
5,500円
⑧おむつ証明書 550円
⑨死体検案書(検案料) 33,000円
※病院での検案 11,000円
■保険外併用療養費(選定療養費)について
| 種類 | 患者様負担の内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 201号室(1人部屋) ※差額ベッド代 | 日額 3,500円(税込) | ・差額ベッドの入室は患者様またはご家族様が希望された場合を原則とします。 ・当院都合の場合は室料の徴収は致しません。 |
| 時間外診察 | 時間外加算相当額が自己負担 6歳以上 650円 6歳未満 1,350円 | 再来の患者様で当院の表示する診療時間以外の時間に、 緊急の必要性がなく自己の都合により診察を希望した場合に徴収致します。 |
■診療記録の開示に要する料金表
開示には開示請求手数料と開示実施手数料が必要です。
開示請求手数料 2,000円
+
開示実施手数料 以下の表でご確認下さい(税別表記)
| 実施の内容 | 手数料の額 |
|---|---|
| 写しの交付 文書をコピーして提供 | 1枚につき 20円(白黒)・30円(カラー) |
| 写しの交付 電磁的記録をCD/DVD等で提供 | DVD-R等:1枚につき1,000円 |
| 医師による説明 | 1件につき 30分以内 5,000円 ・ 60分以内 10,000円 |
| X-P/CT画像 X-P/CT画像等をCDで提供 | CD等:1枚につき1,000円 |
■医療DX推進体制整備加算について
当院では医療DXを通じて質の高い医療を提供すべく、以下のことに取り組んでいます。
〇オンライン請求を行っております
〇オンライン資格確認を行う体制を有しております
〇マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでおります
マイナ保険証の使い方はこちら⇒ クリック
〇医師が電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室等において活用できる体制を有しております
〇電子処方箋発行:対応予定です(経過措置:令和7年3月31日まで)
「医療DX」とは?
「DX」とは「デジタルトランスフォーメーション」の略で、診察や治療、薬剤処方等のサービスの在り方や業務の内容を改善することに、医療サービス最新のデジタルテクノロジーを活用し、患者様やご家族様がより良質な医療を受けられるような体制を構築することです。
■一般処方名加算について
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした「一般名(有効成分名)」を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
「薬の安定供給」や「後発医薬品の使用促進」のため、国の政策として推進されていますのでご理解とご協力をお願いいたします。
■がん性疼痛緩和指導管理料について
当院副院長は緩和ケアに係る研修を受け、その経験を有する医師です。 当院では、がん性疼痛の症状緩和を目的とした神経ブロックを提供できる体制を整備しています。
■在宅医療情報連携加算について
当院では、患者様同意の上、連携する医療施設・介護サービス事業者とICTツールで診療情報を共有しています。
以下にICT連携実績のある機関名を掲載します。
【連携機関名】
訪問看護ステーションえみなる・宇都宮病院・㈱クローバー・居宅介護支援事業所桃の木・居宅介護支援センター仁瑚会・仁愛クリニック
就労継続支援A型すばる・長生堂渡辺医院・テンジン薬局
身体拘束最小化に向けた指針
1.
身体拘束の最小化に関する基本的な考え方
身体拘束は患者の自由を制限するのみならず、患者の QOL を根本から損なうもので す。また、身体拘束により、身体的・精神的・社会的な弊害を伴います。当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を容易に正当化することなく、職員1人ひとりが拘束による弊害を理解し、拘束廃止に向けた強い意志をもち、身体拘束をしない医療・看護の提供に努めます。
2. 基本方針
(1)
身体拘束の原則禁止
当院では医療の提供にあたって、身体拘束を原則禁止としています。
(2) 身体拘束の定義
抑制帯等、患者の身体又は衣類に触れる何らかの用具を使用したり、向精神薬等の
過剰な投薬により、一時的に患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。
3. 当院での身体拘束の基準
(1) 身体拘束の具体的な行為
①徘徊しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、車椅子・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、
手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
⑥車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車
椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やオムツ外しを制限するために、介護服(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開けることのできない居室に隔離する。
(厚生労働省:身体拘束ゼロへの手引きより)
(2)身体拘束の対象とはしない具体的な行為
①身体拘束に替わって患者の安全を守りADL低下させないために使用するもの
・離床センサー(クリップセンサー、フットセンサー、タッチセンサー)、徘徊センサー②検査・治療などの際にスタッフが常時そばで観察している場合の一時的な四肢および
体幹の固定
4. 向精神薬の使用について当院のルール
当院では使用する際は医 師・看護師、必要があれば薬剤師等と協議したうえで使用する。また、向精神薬の使用に
あたっては、必ず非薬物的対応を前提とし、精神症状が軽減し安心して治療が受けられる ために、適切な薬剤を最小限使用する。
5. 身体拘束による弊害
(身体的影響)
・外傷:抑制帯を外そうとして、皮膚の紫斑や裂傷などを起こす場合がある
・筋力の低下:廃用症候群のため筋力低下が起こる
・心身機能の低下・循環不全:行動制限することで著しく廃用症候群が進行する
・深部静脈血栓・肺血栓:血液がうっ滞し、凝縮しやすくなり血栓ができやすくなる
・褥瘡・MDRPU:高齢者の場合、皮膚が脆弱なため皮膚トラブルを起こしやすい
・せん妄や混乱を引き起こす
・食欲の低下や便秘など
(心理的影響)
・尊厳の侵害:自由に行動できる権利(自律尊重原則)が侵害される
・長時間の身体拘束は不安や苦痛などを増強させる
・周囲の人を敵と感じたり、人体実験をされているような恐怖感を感じる
・医療者との信頼関係を崩壊させる
・あきらめ、無力感、生きる意欲の低下
(認知症への影響)
・混乱や興奮の増大による認知機能低下
・うつ・無力感の増大による認知機能低
(医療者に及ぼす影響)
・患者の尊厳を保てないことによるジレンマ
・身体拘束を解除してほしいという患者の気持ちや苦痛に対する心理的苦痛
・拘束することによってますます拘束せざるを得ない状況を作り出してしまう(下図)
(鈴木みずえ:認知症plus転倒予防,日本看護協会出版会,2019より一部改変・追加)
6. 緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合
(1) 緊急やむを得ず身体拘束を行う要件
患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の要件をすべて満たした場合に限り、必要
最小限の身体拘束を行うことができる。
◎切迫性 :患者本人または他の患者等の生命または身体が危険にさらされる可
能性があり緊急性が著しく高いこと。
◎非代替性:身体拘束を行う以外に代替する治療・看護方法がないこと。
◎一 時 性:身体拘束が必要最小限の期間であること。
(2) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の説明と同意
上記3要件については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと、 患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。
(3) 身体拘束を実施する場合は、当院の「身体抑制ガイドライン」に準じて行う。
7. 身体拘束最小化のための体制
院内に身体拘束最小化に係る身体拘束最小化チーム(以下「チーム」)を設置する。
(1) チームの構成 チームは医師、看護師、薬剤師、作業療法士、MSW、管理栄養士、医療安全専門員、事務員をもって構成する。メンバー構成については、医療安全管理指針の構成メンバーとする。
(2) チームの役割
①身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知する。
②身体拘束の最小化に向けたケア計画の立案及び指導を行う。
③身体拘束最小化するための指針を見直し、職員に周知活用する。
④院内の全職員を対象に身体拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。
8. 身体拘束最小化のための活動
身体拘束最小化チーム
(1)
身体拘束ラウンド
チームメンバー、病棟看護師長、病棟看護師が、拘束患者のベッドサイドをラウンドしながら、多職種の視点から拘束解除に向けた検討を行う。
(2)
身体拘束最小化のための研修
①定期的な教育研修(年2回)の実施
②必要な教育・研修の実施および実施内容の記録
(3)
身体拘束の実施状況の報告
月1回の管理会議において拘束率などを報告する。
(4)身体拘束体験
医師・看護師・看護補助者などがシナリオに沿って身体拘束を実施することで、拘束による弊害を体験し拘束をしない看護の必要性を体験する。
(5)倫理カンファレンス
倫理的視点にたち身体拘束の実施や解除ついて多職種で検討する倫理カンファ
レンスを定期的に開催する。
9. 身体拘束をしないための考え方
(1)身体拘束を誘発する原因の特定と除去 身体拘束を誘発する状況には、必ずその人なりの理由や原因があり、医療者の関わり 方や環境に問題があることも少なくない。そのため、その人なりの理由や原因を徹底的
に探り、除去するケアが必要である。
(2)5つの基本的ケアを徹底する
①起きる
人は座っているとき、重力が上からかかることにより覚醒する。目が開き、耳が聞こえ、自分の周囲で起こっていることがわかるようになる。これは仰臥して天井を見ていたのではわからない。起きるのを助けることは人間らしさを追求する第一歩である。
②食べる
人にとって食べることは楽しみや生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。
③排泄する
なるべくトイレで排泄してもらうことを基本に考える。オムツを使用している人については、随時交換が重要である。オムツに排泄物が付いたままになっていると気持ち
悪く、「オムツいじり」などの行為につながることがある。
④清潔にする
きちんと入浴することが基本である。皮膚が不潔なことが痒みの原因になり、そのために大声を出したり、夜眠れずに不穏になったりすることがある。皮膚をきれいにして
おけば、患者も快適になり、また、周囲もケアをしやすくなり、人間関係が良好になる。
⑤活動する(アクティビティー)
その人の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供することが重要である。その人らしさを追求するうえで心地よい刺激が必要である。
(3)身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現をめざす。 身体拘束最小化を実現していく取り組みは、院内におけるケア全体の向上や入院環境
の改善のきっかけとなりうる。「身体拘束最小化」を最終ゴールとせず、身体拘束を最小 化していく過程で提案されたさまざまな課題を真摯に受け止め、よりよいケアの実現に
取り組んでいくことが期待される。 (厚生労働省:身体拘束ゼロへの手引きより一部改変)
(4)身体拘束しないための具体的な看護方法は、「身体抑制ガイドライン」に準じて実施する。
10. この指針の閲覧について
当院での身体拘束最小化のための指針は医療安全マニュアルに綴り、職員が閲覧可能と
するほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族及び地域住民が閲覧できるようにします。
(附則)この指針は令和6年8月1日より施行する。
制定:令和6年8月1日